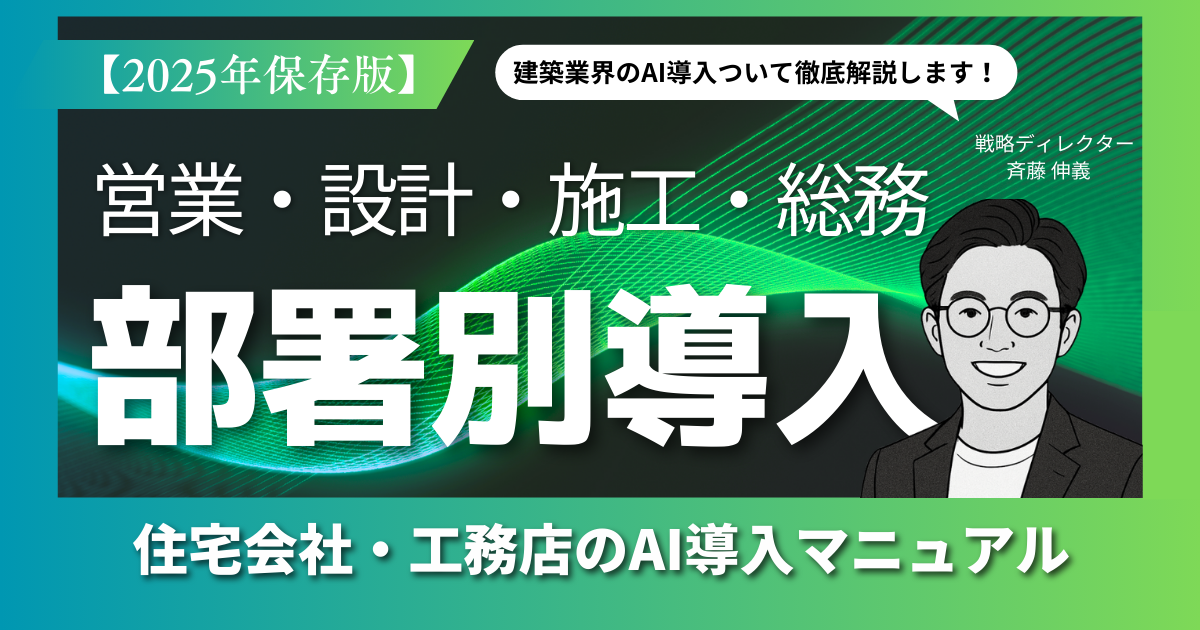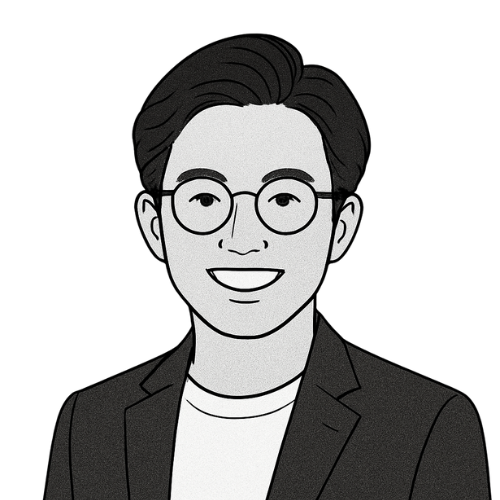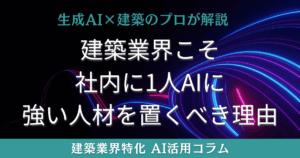前回のコラムでは、Googleが検索を捨て、AIに全振りした情報をお伝えしました。ChatGPTをはじめその他AIツールの進化は凄まじく、建築業界でも「将来的にはAI導入に取り組まないといけない」と考える経営者も多いのではないでしょうか?
しかし、全社的にAIを導入するにあたり「投資に見合う成果が出るのか?」「情報漏えいのリスクはないのか?」といった不安もあるのではないでしょうか。
そこで今回は、建築業界向けにAI導入サポートを行う弊社が、導入の進め方をなるべく専門用語を使わずにわかりやすく解説いたします。ポイントは「全員共通の学び+部門別学び」と段階的に行うことになりますので、その辺りも詳しく解説します。続編では、部門別学びのさらに実務に沿った内容を深掘りしたAI活用についてお伝えする予定です。

【3ヶ月以上かけて導入することが大事】全社で使う共通AI+部署別の専用AIを使い、まずは触ってみよう!
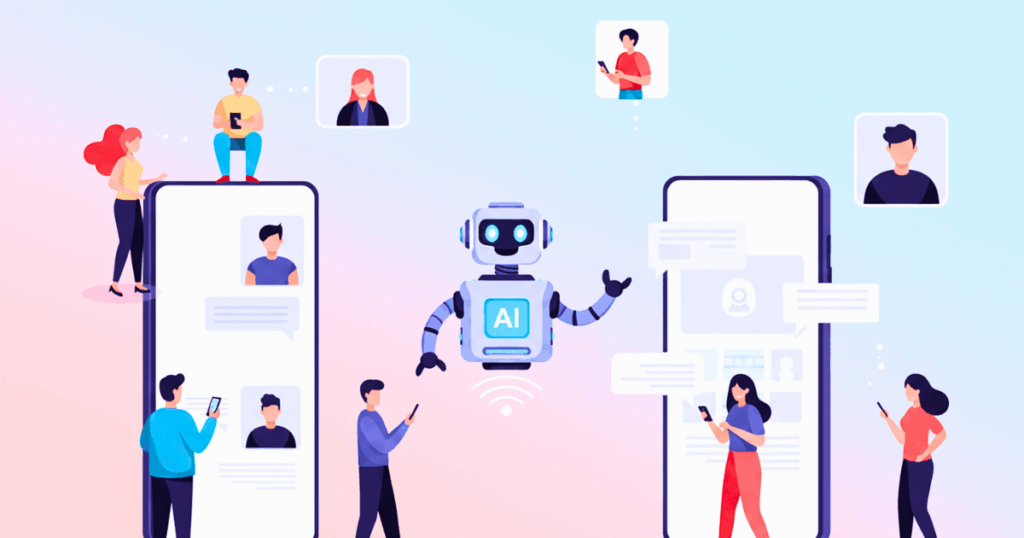
スムーズな導入方法として、まず全社で使える共通AIを導入し、その後に部署ごとの専用AIを段階的に導入する方法が、短期間で成果を実感しやすい進め方になります。
マーケティング・営業・設計・施工管理・総務・経理など、複数部署にまたがる反復作業をAIで自動化すると、大きく工数を削減できるためです。
例えば、チャット対応、物件査定、図面チェックなどのルーティン業務はAIをフル活用できます。スタッフは本来集中すべきプレゼンや商品開発などの高付加価値業務に集中することが可能となるのです。
共通AI:議事録要約・壁打ち・下書き自動化で工数の大幅削減
まず初めに、全社員共通のAIスキルとして必要な、議事録要約、思考の壁打ち、各種文書の下書きを共通AIで標準化すると、全社のムダ時間をまとめて圧縮できます。
工務店の実務では紙・電話・FAXの運用が残る現場も多く、人手不足が重なることで反復作業がボトルネックになりがちです。
実務では、会議の議題をテンプレート化し、録音データからAIを使って要約~タスク抽出までをアウトプットします。今まで議事録作成やタスクや抽出に時間をかけていたものが、会議が終わると同時に完成している状態となります。
壁打ちは、アイデアやまとまらない考えを具体化するのに有効です。AIでルーティン業務を効率化することで本来人がやるべき高付加価値業務を推進するために、壁打ちしながらアウトプットの精度を高めていきます。
また、営業資料や社内ドキュメント作成はAIで初稿を生成し、70%くらいの完成度を目指します。残りの30%は人が手で仕上げる流れにすると、高いアウトプットの資料を短時間・工数削減で作成できます。
これらの共通フォーマット三点セット(要約・壁打ち・下書き)を”同じ型”で全員が使うことが、社内マニュアルや共通言語化する上で、重要となります。
部署別AI:マーケティング・営業・設計・施工管理で成果指標を明確化
マーケティング・営業・設計・現場の各部門で専用AIを使うためには、すべての業務の中でまずは1〜2点に絞り、小さな成功実績を作ることが重要です。
マーケティングではサイト内AIチャットで物件カードの提示精度を高め、フォーム遷移率の改善へ接続できます。
営業ではAIチャットでリード獲得~初期対応の自動化により、返信率や商談化率の改善が期待できます。
設計では、AI搭載CADのゾーニング案や日照シミュレーションで提案速度を上げ、初案合意率や検討時間の短縮を狙えるでしょう。
現場管理では、予知保全やスマートロック連携で点検工数とコストの圧縮を図ります。対応リードタイムで可視化することが重要です。
また、導入時は、住宅特化の導入実績、KPIモデルの提示、補助金支援の体制を確認しましょう。
部署別に成功実績を積み上げ、徐々に対応範囲を広げていくことが重要です。
全部署共通:AIリテラシーと“共通で使うAI”3選

ここからは、より具体的にAI導入を推進するためのツールや動きについて解説いたします。
全部署共通のAI導入を進めるためには、全社員のAIリテラシーをそろえ、議事録要約・思考整理・社内共有の三領域に共通AIを配備することがマストになります。
なぜマストかというと、業務の土台は文書化とコミュニケーションにあり、ここを自動化すると手戻りや伝達齟齬が減るためです。実務では、音声認識と要約を組み合わせた議事録AI、要件整理に用いる対話型AI、決定事項とToDoを一元化する共有ツールを”同じ型”で運用します。
また、住宅特有の用語へ対応する語彙設定を使うと誤認識が下がります。
専門用語を共通認識とするべく、住宅関係者だけでなくお客様も理解しやすい単語で言語化することが重要です。
全社で共通AIの型を定め、横断タスクを一度に自動化する進め方が、導入初期の近道です。
会議議事録の自動要約:記録に時間をかけない
1日が社内会議と議事録作成で終わった…
ほとんどの住宅会社ではまだこのような状態があるのではないでしょうか?そこで、会議音声の自動文字起こしと要約を導入すると、記録工数を大きく抑えられます。
建築分野は商談・契約・設計・施工の各工程で文書管理が重要であり、人によって作成方法が異なったりと、確認・整理に費やす時間が多いのも事実です。
そこで事前に音声認識と要約のワークフローを定型化し、全員が共通フォーマットの議事録テンプレートで管理をすることで、無駄な工数を省くことができます。
音声→要約→タスク化までを一連で自動化し、人的負担を最小化することが重要です。
思考の壁打ち:要件整理・方針比較・リスク洗い出し
お客様への提案書の内容がいまいちで、これだと他社に勝てない…
特に営業にとって契約前のプレゼンは最重要タスクになります。一般的なプレゼンフォーマットを使って、お客様それぞれの状態に合わせた内容にカスタマイズをして資料を完成させることが多いかと思います。そこで、対話型AIで壁打ちを行い「課題→アイデア出し→ブラッシュアップ」を一気通貫で回すと、思考の拡大とアウトプットの精度が高まり、資料の精度が爆上がりします。
自分だけでは浮かばないアイデアや思いもしなかった打ち手が多く出してくれるのがAIの使い所になります。最終判断は人が担い、根拠の裏どりを必ずすることを習慣にすることをセットにすることが重要です。
社内FAQ/ナレッジ検索:営業・設計・施工のQ&Aを即時共有
営業・設計・施工のQ&Aを一元化し、AI検索を整えると、探す時間が短くなり即時対応がしやすくなります。
知識の分散は手戻りと品質ばらつきを招きやすく、ナレッジ共有の仕組み化が生産性向上に寄与するためです。実装では、図面・見積・仕様書・保証・アフターの定番質問を収集し、製品名・工程・部位・注意点のタグで検索可能に備えていきます。
Q&Aの一元化とAI検索で「探す時間」を圧縮する運用が近道です。
マーケティング(広報)部:SNS投稿を量と質で両立させる!

ここからは部署別の課題に対するAI活用について解説します。
マーケティング部がある住宅会社はそこそこの棟数をこなしている規模のところが多いですが、一般的な工務店では社長や広報の人がマーケティングの部分を担っていることがほとんどです。
また、事前準備として施工写真やお客様の声は重要な資産であり、企画や発信をしていく上で重要な情報ソースになるので、幅広く使えるように準備をしていきましょう。
WEBサイトの施工事例だけでなく、Instagram運用や、YouTube運用など情報を発信していく前提として、「発信するコンテンツ」がなければ何も始まりません。
もし、今事例が少ない状態であれば、OB様にお願いをして撮影やインタビューの協力を仰いでいくのが先決かもしれません。今後ますます発信内容のオリジナル性が重要視されていきますので、事前準備をしっかりと行うことが大切です。
Instagram投稿生成:ChatGPT+Canvaで投稿コンテンツ生成を高速化させる
施工写真から「設計のポイント・暮らし方の提案・地域らしさ」をAIで言語化し、Instagramの投稿文とハッシュタグまで連動生成すると、大幅に制作時間を抑えられます。
外部に投稿代行している場合、一度見直してみることをおすすめいたします。今まで投稿のノウハウについては専門的知識やスキルが必要と思われていましたが、AIを使うことで高品質な投稿を自社でも行うことが可能な時代となりました。
むしろこれからは、AIを効果的に使える人材が希少となり、社内に1人はそのような人材を置いておくことが重要と言えます。
運用のコツ:まずは、ChatGPTとCanvaを使えるようにしよう!
なにはともあれ、ChatGPTとCanvaが使えるようになることが自動化への必須条件です。
この方法を使えば、Instagramの投稿案だけでなく、FacebookやXなどの投稿文、YouTubeやTikTokなどの企画なども作れるようになります。
営業:商談をマニュアル化(トーク・追客・見積・図面インプットまで一気通貫させよう)

新人が売れる営業マンになるプロセスとして、トップ営業マンのプロセスをマニュアル化することです。具体的にはインサイドセールスの定型化+フィールドセールスの標準化をし、AI導入で一貫運用すると、商談化率の向上と契約までのリードタイムの短縮が見込めます。
初回接客トークと面談後フォローの台本を自動生成で品質の底上げを行う
トップ営業マンの初回接客の音声議事録を使い、AIツールで文字起こしやトークの順番を平準化することで初回接客と面談後フォローをマニュアル化できます。1つではなく、なるべく多くのサンプル数があると、基本トークの質が高まり、商談の平準化が進みます。
面談後フォローはCRMで一元管理することも重要です。
営業マン独自の基準ではなく、一定のルールに基づき顧客のランクを決めていきます。
以下のように、「次アクション」や「日付」をしっかりと落とし込んでいるかを指標に、営業会議で週次で進捗管理を行うと共通認識や上司からのアドバイスの精度が高まります。
初回面談に次アクションが決まっているか?
面談後24時間以内にお礼のメールを送ったか?
面談後1週間以内に顧客接点を取ったか?
おすすめ実装アイデア:顧客タイプ別テンプレとNGワード集を蓄積する
顧客タイプ別テンプレートとNGワード集について、日々の営業活動から抽出し、AIを使い要件整理や整理をすると、リスク低減と成果の両立が可能となります。
反応率の高いフレーズを収集し、週次でAIを使って整理整頓しテンプレートを改訂しましょう。タイプ別テンプレート×NGワード集の運用をすることで、営業マニュアルとしての財産になります。
インサイドセールス:電話・メール・SMS・LINE等のチャネル別で最適化させる!
多くの住宅会社や工務店の集客の初歩として、顧客から自社のWEBサイトに問い合わせがあると、営業マンそれぞれに振り分けられ、追客がスタートします。また、ある程度規模の大きい会社であれば、インサイドセールス部門があり、面談が決まった段階で営業マンに振り分けがされます。
インサイドセールスとは、顧客との初回接点から商談化させるまでの営業活動を言います。電話・メール・SMS・LINE等を顧客属性やチャネル特性に合わせて文量・トーン・CTAを最適化し、AIでテンプレートを量産すると、反応や開封率、返信の歩留りが上がります。
運用のコツ:反応や開封率・返信率についてAIでアイデア出しを行い、ABテストで最適化
例えばイベント誘致メールの件名・冒頭1行・CTA・送信時刻でABテストを継続し、開封率・返信率で勝ち筋を更新すると、配信の精度が上がります。
データに基づくPDCAとテスト設計はWEBマーケの基本であり、指標に基づく改善が成果へ寄与します。実務は、AIでシグナルスコア高のセグメントへ異なる件名を配布し、結果を自動集計して次回の優先案を提示します。
SMS・LINEは短文と即レス導線を試し、メールは要点→実績→提案→CTAの順を比較しましょう。「測定→更新→再配信」をAIで循環させ、CVまでの距離を縮める運用が有効です。
パンフレット・営業ツール:会社商品や仕様の説明を自動で短文化
営業ツールのトークスクリプトとして、パンフレットや提案書の長文説明をAIで短文化し、関心テーマに合わせて要点を可変表示すると、初回面談の顧客側の理解と信頼関係の構築が進みます。
AIツールのNotebookLMというツールを使うことで、情報ソースを自社のWEBサイトやパンフレットのPDFデータ、YouTube動画などに限定することができ、「○○についてお客様へわかりやすく説明するトークを作成して」と命令するだけで、簡単に作成ができます。
運用のコツ:NotebookLMで営業ツールのトークスクリプトを作成
NotebookLMはGoogle製のAIツールであり、情報ソースを限定できる点が他のAIツールと異なります。
ChatGPTやGeminiといったAIを用いると、WEB上のあらゆる情報ソースから引っ張ってくるので、後の成否チェックが負担となるだけではなく、固有のものであればあるほど情報ソースがないという事態が想定されます。
営業ツールのトークスクリプトの情報ソースは限定的であればあるほど、オリジナルのトークとして生成することができますし、情報の正確性については担保されているので、ほぼそのまま使用することが可能です。
過去の見積や図面をインプットさせ条件入力で初回見積と提案シートの作成
過去の見積と図面をAIへ取り込み、条件入力で初回見積と提案シートを自動生成すると、初動の速度が上がります。
過去の実績としての見積もりを部署で共通管理し、それに紐づいている図面をセットで出力できるように整備をしていきます。
また、顧客属性との関連性を持たせた紐付けを行うことで、よく出る坪数や部屋数、平屋か二階建てかなどをパターン化し、初回面談の際のヒアリングのベースとして活用することも可能です。
運用のコツ:価格表とオプション表を“公式データ”として各営業マンが持っておく
価格表とオプション表を”公式データ”として各営業マンが持っておくことで、初回面談のヒアリングが効率的に行えます。
常にサンプルが増えていく中で、最新の価格データとオプション表をAIで整理し、すぐにアウトプットできると面談時のヒアリング精度が向上し、競合他社との差が一気に広がります。
すでに大手ハウスメーカーや中堅のビルダーでは、初回面談でヒアリング→ラフプラン作成→見積もり提案まで行い、初動の速さで契約まで勝ち取っているのが現状です。
AIを効果的に使うことで、今まで大手ハウスメーカーでしかできなかった初回面談の手法が同じように再現できるので、比較検討の土台から外れることなく、工務店特有の強みを十分発揮できるようになります。
設計・施工管理:パース提案の初回提案UPと点検・品質のAI判定

設計では”好み・制約”を早期にデータ化し、施工管理では”撮影手順・記録形式”を標準化してAI判定へ通すと、提案スピードと現場の見える化が進みます。
国土交通省はAI・IoT等の活用で施工の安全性や効率性の向上を推進し、画像解析やセンサーを用いた現場の自動認識・異常検知の取り組みが示されています。配筋や外壁などの品質検査に画像認識AIを用いる事例が公表されており、人的負担や見落としの抑制が期待されているためです。
設計側では、法規・敷地条件を自動解析し、初期案を複数提示する生成AIの実装やPoCが報告されています。初動の検討効率を高める文脈があります。
設計の嗜好学習×現場の判定標準化を両輪に据えることで、合意形成と品質管理の速度が上がります。
パースのデザインアップ:好み学習で“外さない”初回提案を
施主の嗜好や自社の作風を学習した生成支援を使い、”好み×制約”を踏まえた初回提案を複数提示すると、合意形成までの距離が縮まります。
建築設計支援の生成AIは建築法規や敷地条件の自動解析、複数案の自動生成、初期段階での準拠判断などを特徴とし、検討初期の生産性向上やエラー低減への期待が示されています。実務では、参考写真や過去提案の良否をタグ付けし、スタイル別の雛形を用意、照明・外装・開口比率など微差の連続比較で嗜好を早期に確定することが可能です。
“好み×制約”を同時学習したAIで初案を並列提示し、短時間で方向性を固める運用が有効です。
図面・法規チェックの下準備:条件整理と代替案比較をAIで
「条件整理→適法性の当たり判定→代替案の並列比較」をAIで先に回すと、初期検討の速さと精度を両立できます。
用途地域に応じた容積率や各種斜線などの形態制限は建築基準法の集団規定として体系化されており、前提条件を明示して当たりを取る設計手順が有効です。実務では、敷地面積・前面道路幅員・用途地域・建ぺい率/容積率・高さ制限・日影規制などを入力し、配置/ボリュームの候補を複数提示して、人が意匠・動線・構造の観点で絞り込みます。
AIで前提と代替案を同時に揃え、設計者は判断へ集中する体制が有効的な使い方です。
点検・診断の補助:画像AIで劣化・不具合の一次判定を高速化
屋根・外壁・シーリング等の点検で画像AIの一次判定を用い、最終判定は人が担う二層運用にすると、速度と客観性が両立できます。
国土交通省はPRISMやi-Construction等で画像認識・センサーを用いた自動認識/異常検知や品質管理の高度化を推進しています。UAV/ドローンや動画の標準仕様検討など、点検・診断のデータ取得とAI解析の取組が示されています。
運用では、暗号化・権限管理・多要素認証等の情報保護も併せて整備します。画像AIで一次判定を高速化し、監督者は対策立案へ時間を配分する設計が重要です。
人事・総務:採用トーク事例・会社紹介・スカウト文の開封率を上げる

人口減少が採用難にも容赦なく影響がしてきています。また、ライフワークバランスを尊重することで、よりよい条件の提示や待遇を行える会社に人が集まり、そうでない会社が採用ができないという二極化に陥っている状況です。
採用ができない=生産性が下がる、ということを防ぐためにAI導入で、少数でも生産性が上がる対策について解説してきましたが、必要最低数の社員を確保する必要はあります。
そこで、採用に関してのAI活用として、面接トーク事例・会社紹介・スカウト文をAIで標準化し、指標で検証しながら更新することで、採用コミュニケーションの歩留りが改善できる方法について解説します。
データ利活用と業務標準化は生産性と即応性の向上に資するためです。運用は、職種別の質問バンクと評価軸、会社紹介ストーリー、スカウトの件名と冒頭文をテンプレート化し、開封・返信・面談化のデータで週次更新します。
**広報は、ブログやSNSの学びを要約して採用素材へ展開し、表現を統一しましょう。**AIで”作る→配る→測る”の型を固定し、継続改善へつなげる設計が有効です。
面接トーク事例と評価軸:職種別に質問バンク化を行う
職種別の質問と評価軸をAIでバンク化し、良否例と採点観点を共有すると、面接の再現性が安定します。
手順は、マーケティング・営業・設計・施工管理ごとに「必須経験・求める行動・避けたいリスク」を定義し、深掘り質問(状況→行動→結果→学び)の型で整えます。
現場ブログの要約を背景説明へ用いると、納得感が高まりやすくなります。職種別の質問×評価軸を標準化し、AIで提示と管理を行う運用が近道です。
会社紹介スライド:要点・実績・差別化を短時間で整理し作成
会社紹介スライドをAIで下書き化し、「骨子→要点→差別化」を先に固めると、短時間で説得力のあるスライドを作成できます。
作成手順として、会社のミッション→事業領域→提供価値→数値実績(施工数・満足度・表彰)→社員紹介→選考フロー→FAQの順で固定し、ブログやナレッジの要約で一貫性を保ちます。
骨子を固定し、素材を流し込む運用で、更新と説得力の両立が狙えます。
スカウト文章:開封率改善のABテストをAIで自動提案
スカウト文章の量産とABテスト設計をAIで標準化し、開封率・返信率の結果で継続改善すると、歩留りが上がります。
データ活用と業務標準化は生産性と即応性を高める施策として整理され、ABテストはWEBマーケで一般的な最適化手法として位置づけられています。実務として、職種ごとに「価値提案(成長環境・裁量・評価)」「実例(社員ストーリー)」「応募導線(所要時間・手軽さ)」をテンプレート化し、AIに件名・冒頭文・CTAのバリエーションを生成させます。
社内ブログの学びや現場の温度感を要約して引用すると、伝わり方が安定しやすくなります。“候補者文脈×AB学習”を固定し、開封から面談までの流れを短縮する設計が有効です。
よくある疑問Q&A
- 中小工務店でも効果は出る?
-
A:まずは共通業務の自動化からはじめよう
議事録要約・コミュニケーション下書き・問い合わせ一次応答を”同じ型”で標準化し、テンプレート→自動化→ログ振り返りの順に回すことから始めると、全社員が同時に実感ができます。
共通業務の自動化を第一歩に据え、最小投資で効果をねらう設計が近道です。
- 情報漏えいが心配
-
A:正しいAIリテラシーを学び、情報漏えいのリスクを全社員で学ぶことが必須です。
特に無料で使うAIツールは個人情報は絶対に入力しない、等の一定の使用ルールなどを設けることが必要です。
情報セキュリティのガイドラインは、アクセス制御・最小権限・ログ監査・運用ルール整備を推奨し、誤用や漏えいのリスク低減に有効です。
「参照範囲固定×人の検証」の組み合わせで、漏えいと誤情報のリスクを抑えます。
- コンテンツ品質は落ちない?
-
A:一次生成はAI→最終的には人のチェック
AIの一次生成と人の最終編集の二段工程で、速度と品質の両立を図ることが重要です。
要約・骨子化はAIが補助しやすい一方、文脈適合や正確性の最終判断は人が担うべきです。検索評価でも経験・専門性・信頼性など人の関与を重視する傾向が示されています。
運用は、AIが骨子/草稿を作り、人が根拠確認・事例追加・表現整えを行います。「AIの下書き×人の最終編集」で、伝わる品質を担保しましょう。
まとめ:全社共通→部署別→標準化の順で、成果を積み上げよう!
全社共通の自動化から始め、部署別の成功事例を積み重ね直結、最後に標準化をすることで定着させる三段階を回すとで、実務の落とし込みと業務効率化につながります。
実践で定着させるには短期的に考えず、中長期的に計画立てることが重要です。実際の業務と並行して、新しいことを行うには並大抵の努力では難しい場合がほとんどです。まずは、最初の1ヶ月目でAIリテラシーや全社共通のAI知識の共有を行い、2ヶ月目で部署別AIの導入を行い小さな成功体験をつくる、3ヶ月目で各部署の成功事例と共通フォーマット作成を行うことで、社内マニュアル化や新人育成のツールとして構築していくことが可能です。
sawanでは住宅会社・工務店に特化したAI導入支援を行っています。ここまでお読みいただいた方は、少しでもAIを業務に取り込んでいき、生産性やアウトプットの質を向上させていきたいと思っていただけているかと思います。
まずは、「使ってみる」という最初の一歩が大切です。
そこから業務に落とし込むためにはいくつかの段階が必要になりますので、伴走型で支援を行うsawanのAI導入支援サービスをぜひご活用ください。