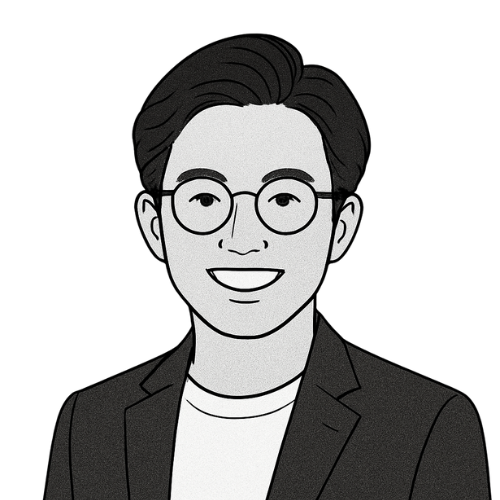Googleが米国でAIモード導入の発表をしましたが、今までのSEO対策は無駄になるのだろうか…?時代の変化が早すぎて戸惑うことはありませんか。結論、今こそ、AIモード時代に向けたSEOの再設計が必要です。
本記事では、従来のSEO手法が直面している課題と、工務店が今後行うべき対策についてわかりやすくご紹介します。また、GEOやLLMOといった最新のポイントも含めて解説していきます。
AIが重視するコンテンツや、すぐに着手できる戦略まで網羅しているため、その日からすぐに自社サイトのコンテンツについての方向性を確認できるでしょう。
日本導入はいつ?GoogleAIモード導入の衝撃と2025年の最新動向
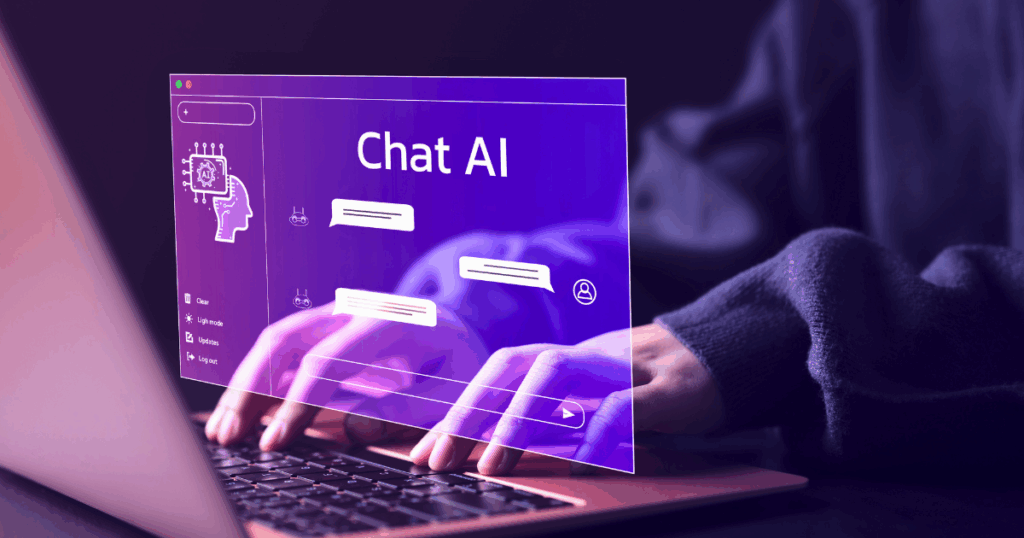
2025年7月時点でGoogle検索のAIモード(AI Mode/SGE)はアメリカでの一般公開から約2か月が経過しました。しかし、日本国内ではまだ正式に展開されていません。
それでもAI主導の検索体験は業界全体に大きな影響を与えつつあり、近い将来、日本国内導入への備えが重要です。過去のAI Overviewsの例から見ても、正式導入は数か月遅れて発表される傾向があります。
工務店を含む住宅業界でも、今のうちから対応を進める必要性が高まっているのです。
米国で始まったAIモード(SGE)の現状 ― 普及率は限定的でも静かなインパクト
現段階で、アメリカ国内でのAI要約型検索(AIモード/SGE)の普及率は2%未満にとどまっています。しかし、検索スタイルが従来型からAI要約型へと静かに移行しており、この動きを読み取って自社対策を進めることが、今後の成長・成果へ直結します。
AIによる即時要約表示の増加により、SEOも「AIに選ばれるコンテンツ」へとシフトしている点に注目すべきです。
なぜ今、AIモードが標準化される前に動き出すべきなのか?
日本ではまだAIモードが標準化されていませんが、この移行期を先読みしていち早く最新のAI検索仕様に最適化しておくことが、他社との差別化につながります。どんなコンテンツがAIに重視され、どのようなウェブサイト構造が評価されるのかを把握し、即座に取り入れることが今後の結果を左右するでしょう。
「AI検索時代」に備えて能動的に対策を進めておく姿勢が極めて重要なのです。
遅くても2026年4月に日本でも本格導入か?迫るAI検索時代のカウントダウン
日本国内でも2025年後半から2026年春にかけて、Googleなど主要プラットフォームによるAI検索の本格導入が予想されています。さらに、この前段階としてベータ版のテスト運用が一部ユーザー向けに2025年夏頃より始まりつつあると予測されています。
従来型SEOだけに依存する手法は今後ますます通用しづらくなるでしょう。工務店や建築業界でも、サイト集客戦略を再設計する最良のタイミングと言えます。
AI要約時代には「どんな情報が引用・要約されるのか」「どのようにウェブサイトが選ばれるのか」をいち早く情報をキャッチすることが大切です。時代に合わせてコンテンツ構築や訴求方法を変化させることが、今後の集客力と業界内のポジショニングにつながります。
AIモードがもたらす「検索体験の激変」―なぜ”WEBに行かない”ユーザーが続出するのか

皆さんも目に触れたことのあるGoogle検索内に実装されたAI overviewが、ユーザーの検索行動を抜本的に変えはじめています。検索AIモードの導入によって、これまでのように複数サイトを巡る必要が薄れ、一問一答型のWeb体験が急激に普及してきました。
実際、AIによる即時要約の登場で多くのユーザーが「Webサイトを訪問しないまま答えを受け取る」場面が日常化しているのです。こうした流れを理解するには、AI技術がどのように検索エンジンの構造や情報取得プロセスを刷新しているかを把握することが不可欠でしょう。
検索→AIによる要約がデフォルトの未来
今や「質問をそのまま打ち込み→AIによる要約提示」が検索の新標準になりつつあります。ユーザーは質問を自然な話し言葉で入力するだけで、AIが複数の信頼できるソースから最適解を抽出・要約し、即座に表示してくれるのです。
その結果、従来主流だった「検索キーワードを打ち込む→リンクを自分で選ぶ→ページを行き来する」手間が大幅に省かれる新しい検索体験が広がっています。こうした効率化の反面、企業サイトや情報発信者には「AIに引用されやすい情報設計や構造設計」が求められているのです。
これまでのSEO戦略に大きな転換を迫られているといえるでしょう。
ページ遷移が激減 ― ゼロクリック時代の到来
AI要約の一般化によって、”ゼロクリック検索”が急増しているのが現状です。ユーザーは検索結果画面で得られた短い要約や回答に満足し、Webサイトを訪問する割合が大きく減少しました。
調査データでは、AI要約が表示された場合には外部サイトへのクリック率が約半分に低下するという結果が出ています。引用元のリンクそのものがクリックされるケースも極めてわずかである実態が明らかになっているのです。
今後の集客施策では、「どうAIに認知・引用されるか」「どんな情報が優先的にまとめられるのか」といった視点が従来以上に重要になるでしょう。
AI要約の”弱点”と「意図通りの答え」にたどり着けない原因
AIによる要約は便利ですが、検索意図や文脈を正確に反映できないケースも多く見られます。AIは大量の情報を高速でまとめて提供できる一方で、「本当に欲しい答え」を外してしまったり、細かいニュアンスや背景を理解できず誤認することがあるのです。
最近の調査でもAIサマリーが誤った内容を自信満々に提示する事例が60%を超えるという結果が出ています。AIの回答が不正確になるリスクへの注意喚起が進んでいるのが現状です。
また、AIが複雑な検索意図や多義語を取り違えたり、出典元が不適切な場合に誤情報を拡散するケースも指摘されています。そのため、サイト側は信頼できる情報を明確かつ論理的に整理し、AIに認識されやすい構造やメタデータ、引用元の明示を徹底する必要があるでしょう。
加えて、AI向け設計では、必要な要素やニュアンスを簡潔に伝える施策が欠かせません。
SEOはもういらない?いいえ「役割」がシフトするだけです

SEOは不要になるのではなく、その役割がAI検索時代へと大きくシフトしています。これまで”検索順位を高めて集客する”ことが主流でしたが、AIは膨大な情報を収集・要約し、ユーザーに最適な回答を直接提示する機能を持ち始めているのです。
そのため、従来型SEOだけで集客を維持するのは難しくなってきました。今後はSEOに加えて「GEO(ジェネレーティブ・エンジン・オプティマイゼーション)」――生成AIやAI検索で自社の情報が引用されやすい最適化――が不可欠となるでしょう。
検索体験と集客力の進化を実現するには、この変化を正しく捉えた戦略転換が最重要課題となります。
従来型SEO:検索上位表示がゴールだった時代
従来のSEOは「特定キーワードで検索結果の上位を獲得」をゴールとしていました。工務店や建築業界の多くが「上位表示」を最重要指標として競い、地域名やサービス内容などを含めたキーワード対策に注力してきたのです。
内部・外部リンク、定期的な情報更新、実績紹介ページの充実なども行ってきました。この方法は確かな集客効果を生み出しましたが、AI時代の進展とともに「順位至上主義」では十分な成果が見込めなくなっているのが現状です。
今後はキーワード対策だけでなく、GEOやAIに評価されやすい構造化が求められます。ユーザー属性・地域性に最適化した設計など、総合的なウェブ戦略がより重要になるでしょう。
これからのGEO:AIに”選ばれる”ための設計思想へ
AI時代のGEO(ジーイーオー)は「AIに引用・推薦される独自性・信頼性・専門性重視の情報設計」が不可欠です。検索順位以上に、建築実績やお客様の声、現場の施工ポイントといった”リアルな体験・データ”を具体的かつ明確に発信することが重要になります。
特に建築系は「EEAT」(経験・専門性・権威性・信頼性)が高く評価されるのが特徴です。実績ページ・顧客レビュー・施工写真などを論理的に整理するほど、AIからの引用・要約対象として優先されやすくなるでしょう。
単なるキーワードの羅列ではなく、会社独自の理念や現場のこだわりが伝わるストーリー型情報設計が、他社との差別化につながります。
事実!AIが引用する約6割が検索20位以内から!GEO重要度の理由
最新の調査によれば、AIが要約・回答で引用する情報の約61%がGoogle検索20位以内のウェブサイトです(AIO引用率データ)。つまり従来のSEOで上位を維持することは現在も「最低条件」となりつつあり、AI時代でもSEOをおろそかにできません。
ただし引用元の4割は20位圏外からも出現しており、「オリジナル性・構造化・EEAT」の高さがAI選出の鍵となる実態も示されているのです。したがって検索順位・GEO両面の対策――上位化維持とAIに選ばれる独自設計――を両立する総合戦略こそ、これからの工務店・建築業界WEBマーケティングの成功条件といえるでしょう。
どの業界もGEO対策は必要?【業種・属性別で重要度が異なる理由】

GEO(ジーイーオー)対策の必要性や優先度は、業界やユーザー層によって大きく異なります。すべての企業が同じテンポでGEO施策に取り組む必要はありませんが、自社の業界環境や顧客属性を的確に見極めることで、最適なアプローチが見えてくるでしょう。
たとえば教育・専門サービス、IT分野など専門知識型業界では、GEOによる「一次情報」発信や用語解説がAIに選ばれやすく有効です。一方、ローカルビジネスや小売は口コミやFAQ構造化などユーザー参加型施策が成果につながりやすい傾向があるのです。
このように、業界ごとに押さえるべきGEO施策のポイントと注意点を明確にすることが、マーケティング成功の第一歩となります。
ITリテラシー高い20〜40代向けBtoB事業は”必須”
20〜40代のITリテラシーが高い層をターゲットにしたBtoBビジネスでは、GEO対策が特に重要です。この世代のビジネスパーソンはAI要約や最新検索機能へのリテラシーが高く、インターネットを駆使した情報収集が日常化しています。
複数製品・サービスを徹底比較し意思決定する傾向があるため、AIに引用されやすい独自コンテンツや最新事例、専門解説記事の充実が不可欠となるでしょう。また、リアルタイムな情報発信や高度なSEO連携と合わせて、継続的・柔軟にデータ更新する体制が競合との差別化に直結するのです。
BtoB領域ではGEOとSEOの両立が、今後ますます集客・信頼性強化の鍵となるでしょう。
高齢者向け/オフライン主流業界は”急ぐ必要は低い”理由
高齢者が主要顧客層、またはオフライン集客中心の業界では、GEO施策の導入を急ぐ必要性は限定的です。近年は70代でもインターネット利用率が約7割、60代では8割超と高まっていますが、生活インフラとして根付く一方、主な情報源は依然としてテレビ・新聞に強く依存する傾向が残っているのです。
中高年層でもYahoo!やGoogleの利用は広がっているものの、AI要約サービスや最新検索技術の積極利用層は限定的といえるでしょう。そのため、こうした分野では市場のデジタル化進展を注視しつつ、社内体制づくりや段階的な施策導入を進めていく形が適切です。
SNSやWEB広告同様、事業・顧客の特性を考慮し無理なくGEO対応の準備を進めましょう。
工務店・建築業界がGEOを優先すべき4つの根拠
工務店や建築業界ではGEO対策が最優先の集客施策となっています。その背景には、
1. 競合との差別化
2. 地域密着型集客の効率化
3. AIに引用されやすい信頼性ある事例・施工データの発信
4. 口コミや顧客レビューを重視した評価アップの実現
という明確なメリットがあるのです。
住宅分野ではネット情報収集に積極的な購買層も増えており、SEOと組み合わせてGEOへの注力が持続的な集客と顧客信頼の維持・拡大に直結します。今からGEO施策に取り組むことで、AI主導時代の中でも安定的かつ優位な集客を実現する基盤づくりが可能となるでしょう。
工務店・建築業界が今日から始めるべき8つのGEO対策【コンテンツ&運用編】

今こそ工務店・建築業界はGEO対策(ジーイーオー)に本格取り組みを始めるべきです。AIがWEB情報を直接収集・引用する時代、施工実績や利用者のリアルな声、地域性や専門性が際立つ独自コンテンツ発信は不可欠となっています。
GEO対策は”AIが引用したくなる信頼性・専門性強化”が柱となるのです。たとえば現場体験や施工写真・工程解説など、他社にない一次情報を積極的に公開することで、SEO+GEOの両輪で成果を引き出せるでしょう。
定期的なコンテンツ更新・FAQ整理もポイントで、「最新&本物」情報発信がWeb集客力の持続的な向上につながります。
その1:GEO対策(LLMO対策)の要|EEAT強化と独自コンテンツ設計の実践法
EEAT(経験・専門性・権威性・信頼性)強化と独自性の高い一次情報発信がGEO/LLMO成功のカギです。AI検索エンジンに選ばれるには、施工事例や専門家の監修・現場スタッフのコメントなどリアリティあるコンテンツが決め手になるでしょう。
記事リライト時は単なる追記ではなく、「数字や根拠・独自データ・FAQや悩み解消型情報」を加え、根拠と論理性を高めてアップデートしましょう。専門家監修や最新データ引用も信頼性向上に有効です。
これによりAIからの評価・引用率が高まりやすくなり、競合との差別化に直結するのです。
その2:課題+解決策のページ構成で”AIに引用されやすい”を実現
「課題→解決策→実例」というページ構成がAIに引用されやすい鉄則です。顧客の悩み(例:資金計画、土地選び、耐震対応など)をまず明確化し、その具体的解決策や自社の強みをストーリー・実績データで客観的に示しましょう。
FAQ・チェックリスト・ランキングなどの形式もAIが参照しやすく、AI要約精度向上に効果的といえます。現場主義の一次情報を組み込むことで、ユーザーにもAIにも分かりやすい信頼性の高い発信が可能となり、引用・評価につながるでしょう。
その3:自社ならではのUSP(強み)を具体化する3ステップ
USP(ユーエスピー)=独自の強みを明確化するとAIにもユーザーにも選ばれやすくなります。1つめは顧客アンケートや成約理由の整理で「自社独自の特徴」を洗い出し、2つめはその強みが伝わる体験談や現場ストーリー・スタッフ紹介などを盛り込みます。
3つめは競合比較データや写真・独自の成功事例を併せて根拠を補強し、「なぜ自社が選ばれるのか」を論理的に訴求しましょう。独自性と現場リアルを前面に出すことがAIからの評価・引用強化を実現するのです。
その4:既存記事を「削除せず残す」理由とEEAT持続の重要性
既存記事は削除せず残すことで、EEAT(専門性・権威性・信頼性・経験)の資産としてAI時代も価値が高まります。長年にわたり蓄積した記事や実績ページは、ウェブサイトの信頼評価や権威性を押し上げ、AIや検索エンジンが”引用する根拠”として高く評価するのです。
特にGoogleは歴史や情報量・コンテンツ更新履歴を重視する傾向があり、古い内容も適切なリライトと情報追加で鮮度・価値を維持できるでしょう。AI要約時代のSEO・GEO両方で”過去記事=信頼資産”と捉え、内容アップデートと全体管理でEEATを持続強化する姿勢が不可欠となります。
その5:AI引用状況のセルフチェック手順[例:Gemini等で確認]
AI引用率チェックにはGemini等の生成AIチャットで「自社の情報が回答・引用されるか」テストするのが効果的です。ユーザー視点とAI視点の両面から、新しいプロファイルやシークレットモードで”質問キーワード”を変えつつ何度も検索を試み、自社サイトや特定ページの引用有無・頻度を確認しましょう。
引用が安定しない場合、FAQ形式や一次情報の追加、専門性・実績根拠の強化が有効策となります。AIの回答傾向は随時変化するため、定期的にセルフチェックとコンテンツメンテナンスを繰り返す運用が重要となるでしょう。
その6:被リンク・外部言及獲得の全実践パターン
質の高い被リンク・外部言及を増やすことがAI時代の信頼性・評価向上のカギです。自社サイトがAIに見つけられやすくなるためには、多様な手法で被リンクを獲得することが不可欠となります。
具体的には「業界メディアへの寄稿」「プレスリリース配信」「取材・インタビューの受け入れ」「現場事例やキャンペーンのSNS拡散」「お客様の声や協力先企業のWeb等での紹介」が挙げられるでしょう。さらに「リソースページ登録」「イベント協賛」なども有効とされています。
質の高いコンテンツ作成や独自調査レポート発信も自然な外部リンクを生むため、全ての施策を継続的に実行しましょう。繰り返しの運用が、専門的・地域密着型の証明となり、GoogleやAIによる評価軸を強化するのです。
その7:PR・SNS・メディア連携で「AIが見つけやすい」ブランドへ
SNSや外部メディア連携による定期発信が「AIに見つかるブランド化」の近道です。専門誌や地域Webメディアへの寄稿、YouTubeやInstagramで現場の様子・施工プロセス動画を発信し、地域イベントやキャンペーン、参加情報も広く拡散しましょう。
オウンドメディアでの深掘り記事やインタビューも、共感・引用を呼ぶ要素となります。実績・体験のストーリー化やニュース性のある発信も有効で、これにより多様なキーワード・事例でAIやGoogleの探索範囲に自社情報が掲載されやすくなるでしょう。
SNS×メディアの運用を組み合わせ、定期的な拡散・露出戦略を怠らないことが重要です。
その8:社内運用|3カ月で仕組み化する実行スケジュール
GEO施策は短期集中ではなく継続運用・仕組み化が成功の条件です。初月は現状分析と主要課題・チャンス領域を洗い出し、2カ月目は具体タスク・役割分担・定例ミーティングや進捗管理の型作り、3カ月目は評価基準作成と運営型PDCA体制の定着を目指しましょう。
四半期単位で成果・進捗を振り返ることでノウハウが蓄積され、属人化せず安定・継続的にGEO運用が可能になるのです。外部支援会社やPRパートナーとの連携も生産性・効果向上に有効でしょう。
SEO・GEOを一過性で終わらせず、仕組みとして根付かせることが中長期のブランディング成功には必須となります。
SEOは終わりではなく「GEO」への進化 ― 今こそブランド再点検を

SEO(検索エンジン最適化)は不要になるのではなく、GEO(生成AI最適化)とともにデジタル時代の根幹を成します。従来のSEOはWebサイトへの流入・順位維持という役割を果たし続けるでしょう。
また、AIによる回答生成やGEO対策の重要度が高まっており、「SEO+GEO」の二本軸でブランド力や情報発信力を総合的に強化することが有効とされています。AIも検索エンジンも、過去から積み上げたコンテンツ・実績・信頼性を評価基準とするのです。
今こそ自社発信の全体像を再点検し、「AIに引用される=新たな認知経路」として最適化する好機といえるでしょう。
SEOとGEOが補完し合う「二本立て時代」が到来
これからはSEOとGEO、両方を戦略的に組み合わせる”ハイブリッド時代”が王道です。SEOは従来どおりWebサイトへの検索流入を最大化し、GEOはAI検索や生成AIによるダイレクト回答でブランド想起・認知拡張を担います。
FAQや構造化データなど”SEO基盤”上に、GEOの視点でエビデンスやストーリー性、一次情報の強化を重ねることで、AIにも検索エンジンにも選ばれるコンテンツ設計が可能となるのです。この二本立て戦略が業種問わず新標準となり、Web集客やブランド価値向上の最大化へとつながるでしょう。
“終わり”ではなく”アップデート” ― いま見直すべきポイント総まとめ
SEOは終わりではなく、継続的なアップデートが求められる時代です。最も重要なのは、E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性・経験)の強化と、検索意図や体験に根差した疑問解決型コンテンツへのリニューアルとなります。
Googleの2025年最新版の品質評価ガイドラインでは、E-E-A-Tの徹底が順位上昇の条件と明記されているのです。また、アルゴリズムアップデートは頻繁に実施されるため、ユーザー行動や検索クエリ傾向、主要指標をこまめに分析し、古いコンテンツのリライト・追加情報の更新を習慣化しましょう。
全記事の価値を”AIにも人にも支持されるWeb資産”として保守することが、GEO・SEO両軸の成果向上に直結するでしょう。毎年業界動向や自社の成果を数値で見える化し、PDCA(計画・実行・検証・改善)の高速サイクルで柔軟に運用体制を強化してください。
何から始める?すぐできる「AI時代の情報発信」手順
「FAQ構造」や「体験型エピソード」を採り入れた情報発信がAI・ユーザー双方に選ばれる第一歩です。まずはFAQ(よくある質問)やリアルな体験のエピソードを盛り込んだ記事を1本、新規公開またはリライトしましょう。
各担当者から現場の実体験や専門視点をヒアリングし、編集担当がAI目線で構造最適化を実施するのです。公開1カ月後にAIツールで引用テストを行い、引用例・アクセス数・問い合わせ数などの可視化を進めてください。
社内共有や担当者ローテーション、月ごとのテーマ決めでPDCA体制を素早く構築し、繰り返し運用改善サイクルを回すことが成果アップの分岐点となるでしょう。FAQ活用はSEO面でも「検索意図直結・内部リンク強化・情報鮮度維持」で高い効果が認められています。
まとめ
AIとユーザー双方に選ばれるGEO・SEOのハイブリッド戦略が、これからの集客と成果創出の鍵です。本記事では、AIモード・SEO最新動向から、工務店(こうむてん)を含む全業界で役立つGEO・LLMO施策の実践ポイントを解説しました。
単なる検索順位追求にとどまらず、自社ならではの専門性・現場体験・独自ノウハウを積極発信し、”ブランド資産”を継続的に育むことが、新時代の最大の競争力となるでしょう。今こそ古い常識を見直し、小さな一歩からPDCAを早期始動させ、”AI・ユーザー双方に響く情報戦略”へアップデートを始めてください。
sawanではAI時代に求められるGEO戦略を取り入れながら既存のSEO対策と両軸で行なっていきます。地域NO.1店になるべく、工務店・建築業界のWEB集客をAIを駆使していち早く取り組んでいきませんか?